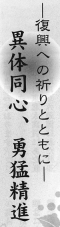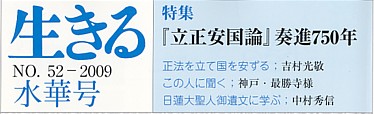| 「異体同心、勇猛精進」:「生きる」 |
 |
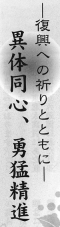 |
 |
「異体同心、勇猛精進」
富士市長学寺住職 吉村光敬
撃鼓唱題(しょうだいあんぎゃ)
私はお坊さんの修行で、唱題行脚(てっこうきゃはん)が好きです。行脚用の衣に着替え、手甲脚絆をし、天台笠を被り、団扇(うちわ)太鼓を持つと毎回気持ちがピンとする。大きな声でお題目を唱え、団扇太鼓をたたき、街頭を歩くとなんとも言えない充実感がある。唱題行脚は、自分自身の修行であるが、この唱えているお題目が、亡き霊を供養し、人々の平和や安全を祈願できると思うと嬉しくなるのである。
そんな気持ちを初めて実感したのは、身延山僧道実修生の時で、この時の体験は、身延山久遠寺『みのぶ』平成三年五月号「身延山僧道実修生を終了して」に
ーこの一年間、多くの尊い経験をしましたが、その中でも私が一番感動した事があります。それは、実修生活が始まった日の事です。実修生は身延山本院と寝泊りしている信行道場を、毎朝毎夕、撃鼓唱題して行くのですが、その撃鼓唱題の仕方を教わりながら下山する時でした。前の方に身延山にお参りに来ていた方が、私達の姿を見て立ち止まり、私達が通り過ぎるまで合掌し、礼拝されていたのです。私は、その尊い姿に胸打たれ、自然に目に熱い物が込み上げてきました。私は、いままでこんなに純粋な気持ちになったことはありませんでした。そして、こんなに尊い人々が集まる身延山で修行を出来ることを幸せに思いました。普段見慣れている合掌も、いざ自分がこういう立場になってみると、しかも身延山で体験してみますと、心が洗われる気持ちになりますーと私自身が書いています。
今でもその時の気持ちは鮮明に覚えていて、この体験があったからこそ、唱題行脚に精進できることと感謝しています。
寒行
そんな私の唱題行脚の原点は、私のお寺(自坊)での寒行です。先代住職の光篤上人から修行するようになり、毎年寒の入りから節分まで四週間、毎晩午後七時より檀信徒の皆様とお題目を唱え、団扇太鼓をたたき、約三キロの同じ道程を約四十五分で行脚します。日によって参加人数が変わりますが、幼稚園や小学校のお子さんの世代、お父さんお母さんの世代、お祖父さんお祖母さんの世代の十五人位が参加しております。そして、寒行の道中では、合掌のお姿でお迎えして頂いている皆様や、お子さん達が手を振り「がんばってー!」の声援があり、こちらとしては自分自身の修行なのに恐縮するのと同時に、そのお姿や声援が、ご一緒に修行して下さっているのだと共感し、修行する側とお迎えする側が支え合っていることを実感し、嬉しく思うのであります。

また、私の子供達も寒行に参加して、長女が『社会を明るくする運動』の作文に寒行の事を書きましたので、ご紹介したいと思います。
「寒修行」富士市立吉永第一小学校六年 吉村華映手
私の家はお寺です。小さい頃から、お父さんやおじいちゃんがお寺のお仕事をするのを、当たり前のように見てきました。お寺の仕事には、お葬式、法事、お盆の法要、たなぎょうなどがあります。たくさんあるけど、私が一番興味をもったのは、寒修行でした。
幼稚園の年少の頃、寒修行に出かけていくお父さんとおじいちゃんを見て、かっこいいと思ったからです。
寒修行とは、寒の入り(小寒から大寒の約十五日間と大寒から節分までの約三十日間)から節分までの一年間で最も寒い時期に「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えながら行脚することです。何で、この一年間で最も寒い時期に歩くかというと、特に寒い時期に修行すると、よりご利益があると言われているからです。
私は、お父さんやおじいちゃんと一緒に歩いてみたくて、お母さんに何度も何度も頼みました。「華映手(かえで)ががんばるなら一緒に行ってあげるよ。そのかわりにちゃんと歩くんだよ。」と、お母さんと約束して、初めて私も寒修行に出かけました。
三才の私には、ジャンパーを着ていても冬の夜はとっても寒く感じられました。お母さんは、弟を背中におぶり、一緒に歩いてくれました。地域の人たちも一緒でした。
「ドン!ドン!」
お父さんとおじいちゃんの打つ太鼓の大きな音が、夜の寒くピンと張った空気の中、静まりかえる吉永の地区中に響き渡ります。そして、お題目を唱えながら歩き続けました。とても長い道のりでした。(毎日、これを続けているお父さんとおじいちゃんはすごい!一緒に歩いている私もすごい!)と嬉しくなりました。
私のお父さんは小学生の頃から、約三十年以上、毎日、行っています。私は、三才の時に始めて、今年で九年になりました。(何で歩くんだろう。家でやればいいのに。)と思ったこともありました。お父さんに聞いてみると「吉永に住あ人々が、平和で安全で暮らせるように、吉永を見守りながら歩いて回るんだよ。寒い中を歩いて回るからこそ、ご利益があるし、そうすることが自分のためにもなるんだよ。」と教えてくれました。みんながみんなのことを思いやれば、平和で安全な吉永になる。日本中の人がそう思ったら、世界中の人がそう思ったら。こんなちょっとしたことが、みんなの安心、平和につながっているんだ。「平和」ってすごく大きなことで、自分がどうにかできることではないと思っていたけれど、私も、平和を作る一人になれる。それまでは、たまに行きたくないなと思ってしまう日があったけれど、これを聞いて私もがんばろうと思うようになりました。毎日続けることが、みんなのためであり、私のためであると。これを読んだ私自身、みんなの平和と安心を願い、寒行をがんばって続けていこうと思いました。
聞信口唱
日蓮聖人は『観心本尊抄(かんじんほんぞんしょう)』の結文に「一念三千(いちねんさんぜん)を識(し)らざる者には仏(ほとけ)、大慈悲を起こ
し、五字の内(うち)に此(こ)の珠(たま)を裏(つつ)み、末代幼稚(まつだいようち)の頸(くび)に懸(か)けさしめたもう。」と述べられ、お釈迦様(本仏釈尊)は、あらゆる功徳をおさめている南無妙法蓮華経により(題目下種)、私達(末法の衆生)の救済をお示しになられました。
また、その修行方法として、『四信五品紗(ししんごほんしょう)』に
「問う、汝何(なんじなん)ぞ一念三千の観門(かんもん)を勧進(かんじん)せずして唯(ただ)題目ばかりを唱(とな)えしむるや。答えていわく、日本の二字に六十六国の人畜財(にんちくざい)を摂尽(しょうじん)して一(ひとつ)も残さず。月氏(がつし)の両字に量(あ)に七十
箇国なからんや。(中略)問う、其の義(ぎ)を知らざる人、唯だ南無妙法蓮華経と唱えて解義(げき)の功徳(くどく)を具(ぐ)するやいなや。答う、小児乳(ちち)を含むに其(そ)の味(あじ)を知らざれども自然(じねん)に身(み)を益(やく)す。耆婆(ぎば)が妙薬(みょうやく)、誰(だれ)か弁(わきま)えて之(これ)を服
せん。」と、お題目を信じて唱える修行をすすめられています。私達はこの教えを信じ、唱題行脚の修行をするのです。すなわち、私達はお題目を聞いて(聞法)・唱えて(信心)・唱えて(口唱)・聞かす(下種)のです。
阪神淡路大震災第十七回忌唱題行
本年一月十七日、阪神淡路大震災第十七回忌追悼法要並びに唱題行脚が修行されることを伺い、参加させて頂きました。当日は、神戸市須磨区の本立寺様に於いて阪神大震災追悼会に参拝、その後兵庫区に移動し、美法会(みのりかい)(本門法華宗青年僧侶の有志による会)のお上人方や、法華宗有志のお上人方と共に、大震災で亡くなった御魂に追善供養、ここまで復興した苦労と努力に感謝のお題目をお唱えいたしました。神戸の復興した町並みを拝見し、日本国中の祈りが叶ったと感じ、これからも被災された皆様の心の復興を祈り、ただお題目を唱えることを誓願し、帰路につきました。しかし、それから僅か二ヶ月後の三月十]日、東日本大震災が起こりました。
お題目の祈り
今日現在まで私自身、被災地に赴くことができないでいる。そんな自分が嫌になることもあるが、今一度自分が何をできるのかを慎重に考え、冷静に行動したいと願っています。「大地はさゝばはつるるとも、虚空(こくう)をつなぐ者はありとも、潮のみちひぬ事はありとも、日はい西より出つるとも、法華経の行者の祈(いのり)のかなはぬ事はあるべからず。」『祈祷紗(きとうしょう)』
このように日本の大地が異常事態になろうとも、お題目を唱える者の祈りは必ず叶うと日蓮聖人は示されております。私達ができることは、まず犠牲者のご冥福を祈り、被災地の一刻でも早い復興を祈ることです。
修行中の実修生と合掌礼拝された方、寒行での修行する側とお迎えする側、このお互いの支え合いが、お題目の祈りではないでしょうか。
「異体同心(いたいどうしん)なれば万事(ばんじ)を成(じょう)じ、同体異心(どうたいいしん)なれば諸事叶(しょじかな)うことなし。『異体同心事(いたいどうしんのこと)』
被災された方と励まし支援される方が、支え合い、ともに祈れば、万事(復興)を成じます。私達は被災者とともに、犠牲者のご冥福と被災地の一刻でも早い復興を祈り、お題目をお唱えいたしましょう。
本門八品上行所伝本因下種の南無妙法蓮華経
(本門法華宗布教誌「生きる56-2011号」)
|
 |
 |
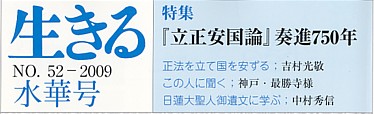
「生きる」水華号
「 正法を立て国を安んずる」
静岡県富士市・長学寺副住職 吉村光敬
奏進より七五〇年の今、現在
日蓮聖人が、文応元年(一二六〇)七月十六日『立正安国論』を鎌倉幕府に奏進なされて、本年、平成二十一年(二〇〇九)は、七百五十年をお迎えします。
『立正安国論』の冒頭で、
近い正嘉元年(一二五七)のころから今年文応元年(一二六〇)にいたる四箇年の問に、大地震や大風などの天変地異が続き、飢饉が起こり、疫病が流行して、災難が天下に満ち、広く地上にはびこっています。そのために牛や馬はいたるところで死んでおり、骸骨は路上に散乱して目もあてられず、すでに大半の人びとが死に絶えて、この悲惨な状態を悲しまない者は一人もおりません。(現代語訳)と、日蓮聖人が生きておられた鎌倉時代の悲惨な状況に心を痛めております。
では、現代の状況というと、平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年の新潟県中越地震、平成十九年の能登半島地震、平成二十年の岩手・宮城内陸地震等の大地震があり、異常気象による災害が多発し、最近では、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)や、新型インフルエンザの疫病が流行しています。また、飽食の時代と言われていますが、日本の食料自給率は低下傾向にあり、現在はカロリーベースで40%と先進国最低水準となっていることを考えると、日本は飢饉状態であるといえます。
このような災難が起こっている現代日本の状況を日蓮聖人が見たならば、七百五十年前と何ら変わっていないとお嘆きになり、心を痛められることでありましょう。
まして、現代に生きている私達も、次々におこる災難に心が痛み、今後の日本はどうなってしまうのかという不安の中で日々暮らしているのが現状です。
日蓮聖人が鎌倉時代の悲惨な状況の中で、人々の心の痛みを無くすため、これからの日本を平和で安らかな国にするために『立正安国論』を奏進されて七百五十年を迎える本年、私達は七百五十年前と同じ災難が起こっていると自覚をし、これからの日本を平和で安らかな国にするために、『立正安国論』を真剣に拝読し、そこから今何をすべきかを真剣に考えていかなければならないのです。
日本国の静謐(せいひつ)を願う
『立正安国論』は、日蓮聖人が宿屋入道を通じ、前執権北条時頼に奏進された勘文です。時頼は前執権といえども、事実上の最高権力者(現在の総理大臣と言い換えられる)であることを日蓮聖人は承知の上で奏進されています。
『立正安国論』は私的な勘文であるとされているのですが、その理由を述べますと「勘文」とは時の幕府(政府)から諮問を依頼された学者などが由来・先例等の必要な情報を調査して報告を行った文章のことでありまして、『立正安国論』の場合は、その諮問依頼なく奏進されたものであるからです。
『立正安国論』の執筆の動機として、『安国論御勘由来』に、
正嘉元年八月二十三日午後九時頃、前代見聞の大地震があった。同二年八月一日には大風。同三年大飢饉。正元元年には大疫病。同二年にも四季に亘って大疫病が止まなかった。そのため国民の大半は死に絶えてしまった。
〜中略〜
日蓮も世間の状況を見て、これを一切経の文に照らし合わせて考えてみると、いろいろな祈祷に効験が無く、かえって災難を増長する理由を知り、その証拠を見出すことができたのある。そこで経文をもとに一通の勘文をかきあげて、その名を立正安国論と題し、文応元年七月十六日、曳宿屋入道を通じて、故北条時頼殿に奏進したのである。(現代語訳)
とあり、天変地異による悲惨な日本の状況を目の当たりにして、執筆されたのであります。
『立正安国論』の内容は、旅客と主人との問答形式で、
第一問答は、災難の原因は日本国民が正法に背いている事(謗法)を明らかにし
第二問答は、災難の原因の証拠としての『金光明経』、『大集経』、『仁王経』、『薬師経』の経典の文を挙げ
第三問答は、謗法の僧が実在する事を示し
第四・五問答は、法然の『選択集』(せんちゃくしゅう)が災難の原因である事を説き
第六〜八問答は、経典の文を挙げて法然の念仏を禁止することで、災難が防ぐことができることを示し
第九問答は、正法(法華経)への帰依を勧め
第十番で、旅客は正法への帰依と、正法の布教を誓います。
第七問答で客が、先ず国家の安穏を祈って、安国を確立してから、仏法(正法)を立てるべきではないのかという質問があります。
世の中が平和であり、国土が安穏であることは、国王から民衆にいたるすべての人びとの願いであります。思うに、国は仏法によって繁栄し、仏法は人によって貴ばれるものです。もし国が滅び、人がなくなってしまったならば、いったい誰が仏法を崇め信じるでしょうか。誰も信じる者はいないでしょう。でありますから、まず国家の安穏を祈って、その後に仏法の流布をはかるべきであると思われます。(現代語訳)
この質問に対し、主人である日蓮聖人は、
およそ災難をはらい除く方法は、仏教にも仏教以外の教えにもいろいろとあって、具体的にあげることはむずかしいのです。しかし、他の教えはおいて、仏教の中でいえば、正法を謗(そし)る人を禁じて、正法を信ずる人を重んずるならば、国中は安穏で天下は泰平になるであろう、と私は考えるのです。(現代語訳)
と答え、正法の確立が先決であり、謗法(ほうぼう)の人々を禁じてから、正法による国家の安泰を祈ることにより、国中が安国になるという、日蓮聖人独自の安国論を示されています。そして、日本国民を救うことができるのは、唯一法華経の信仰であり、
汝早く信仰の寸心を改めて速やかに実乗の一善に帰せよ。しかればすなわち三界は皆仏国なり。仏国其れ衰へんや。十方は悉く宝土なり。宝土何ぞ壊(やぶ)れんや。国に衰微(はえ)なく、土に破壊なくんば、身はこれ安全にして、心は是禅定ならん。此の詞、此の言信ずべく崇むべし。と法華経信仰を勧め、日本国の安穏と日本国民の心の平和を祈っているのです。
予言の的中
さて、本論で注目したいのは、他国侵逼(たこくしんぴつ)の難です。(他国侵逼とは、他の国から日本が侵略されること)
第九問答で、日蓮聖人は、
薬師経の七難のうち五つの難はすでに起こって、外国からの侵略と国内の戦乱という二つの難が残っています。大集経の三つの災いのうち二つの災いはすでに顕われましたが、戦乱の一つがまだ残っています。金光明経に説かれるさまざまな災禍はほとんど起こりましたが、外国からの侵略という災難だけはまだ現われていません。仁王経の七難のうち六難は今さかんに起こっていますが、四方の賊が攻めてきてこの国を侵すという難だけは現われていません。そのうえに前に引用した仁王経の文にも、「国が乱れる時はまず悪魔が力を得てはびこり、悪魔が乱れるから万民が悩まされる」とありました。この経文に照らし合わせて現在の日本の状況をよく考えてみますと、まさしく悪魔が力をふるって、そのために多くの人びとが倒れ死にました。このように経典に説かれたさまざまな難がすでに起こったことからみれば、残りの災難も必ず現われるに相違ありません。もし残りの災いである内外の戦乱の二難が、選択集の謗法の罪によって連続して起こってくるようなことがあったならば、その時はどうされますか、どうすることもできないでしょう。(現代語訳)
これは、経典に示されたさまざまな災難がすでに起こったことからみれば、残りの災難が起こることは間違いなく、他の国からの侵略が必ず起こることを予言されおり、実際にこの後、日本に蒙古襲来が起こるのです。
蒙古襲来について、日蓮聖人は『安国論御勘由来』に
安国論を奏進してから九年を経て今年の正月、大蒙古国から国書が届いたが、それを見ると、日蓮が安国論に予言したことが割符を合わせたように符合したのである。(現代語訳)
と述べられ、『立正安国論』奏進の文応元年(一二六〇)の九年後の文永五年(一二六八)一月に、蒙古から国書が届き、『立正安国論』の予言が的中したとされ、また『種種御振舞御書』の冒頭で
去ぬる文永五年(一二六八)の正月十八日に、西方の大蒙古国より日本国を攻め寄せるとの内容をもった国書がもたらせました。これは日蓮が去る文応元年(一二六〇)に奏進した立正安国論に予言した他国浸逼の難と少しも相違せず符合したものです。(現代語訳)
とあり、この国書は、蒙古の要求に応じない場合は、武力をもって侵略するという内容であることから、他国侵逼の難であると日蓮聖人は認識され、同じく『種種御振舞御書』の中には、
身延に入ってまもない文永十一年(一二七四)十月に、大蒙古国が日本に攻めよせ、壱岐・対馬の二ヶ国を奪い取っただけでなく、太宰府も破られ、少弐入道(しょうににゅうどう)・大友等は、これを聞いて戦わずに逃げ出し、そのほかの兵士たちもおおかた討ち殺されてしまいました。再び攻め寄せてくるならば、この日本国を弱々しいと見くびって来るでしょう。(現代語訳)
と、文永十一年(一二七四)の文永の役を述べ、「又今度よせくるならば」と弘安四年(一二八一)の弘安の役を予言されている。
つまり、日蓮聖人は『立正安国論』で他国侵逼の難を予言され、それは蒙古襲来により証明されたのである。
現在に照らし合わせて
蒙古襲来は、相手側の蒙古軍の失敗ということで、日本は外国からの侵略を防ぐことができたのであるが、これからの日本に他国からの侵略が無いとはいえない。それは最初に述べた通り、現代の日本は地震等の災害が発生し、疫病も蔓延している現実からすると、あとは他国からの侵略が起こると考えられるからです。
それも、蒙古襲来のように他国の軍隊が日本を攻撃するという侵略ではなく、私達の心の侵略です。
現代に生活している私達は、意識しないうちに欧米型の生活様式を取り入れて、それが豊かさの象徴としています。しかしながら、生活様式を取り入れることにより、知らず知らずに、考え方まで欧米型になっているのではないでしょうか?
僕が何故この様に感じるかというと、現在の日本国は憲法第九条で
1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。と「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を約束し、平和の国日本を世界に宣言し、平和憲法による世界平和実現を日本から世界に示したのです。
しかしそれは、日米安保条約があることが前提という側面もあり、他国によるミサイル発射実験に対する世界情勢の反応を見ておりますと、それぞれの国が自らの国益だけを考えているのではないかという印象が否めません。自分達さえ良ければよいという自己中心的な考え方を改めた上で、国家間の安全保障を考え直し、日本独自の平和憲法による、世界平和の実現を全世界に示す必要があると思います。
今、そして未来の平和のために
ここであらためまして、これからの日本を平和で安らかな国にするために、今何をすべきかを『立正安国論』に求めますと、
帝王は国家を基として天下を治め、人臣は田園を領して世上を保つ。しかるに他方の賊来りてその国を侵逼し、自界叛逆してその地を掠領(りやくりょう)せば、あに驚かざらんや、あに騒がざらんや。
国を失い家を滅せば、何れの所にか世を遁(のが)れん。汝すべからく一身の安堵(あんど)を思わば、先ず四表の静誼を祷(いの)るべきものか。と日蓮聖人は示されています。
まず、祈るのは、国家が平和であることであり、自分だけの安堵ではありません。国家全体が平和であってこその自分の安堵になるのです。つまり、日本の平和があって世界全体の平和となり、はじめて個人の平和が保障されるのです。そのためには、正法である法華経を立て、日本が平和で安らかな国になるよう、お題目を唱えこと。これこそが、世界平和の実現であり、日蓮聖人が自らの命を顧みず『立正安国論』を奏進された恩に報いることができる唯一の方法です。
世界の平和のため、日本の平和のため、私達自身の心の平和のために。
本門八品上行所伝本因下種の南無妙法蓮華経。
(参考文献日蓮聖人全集)